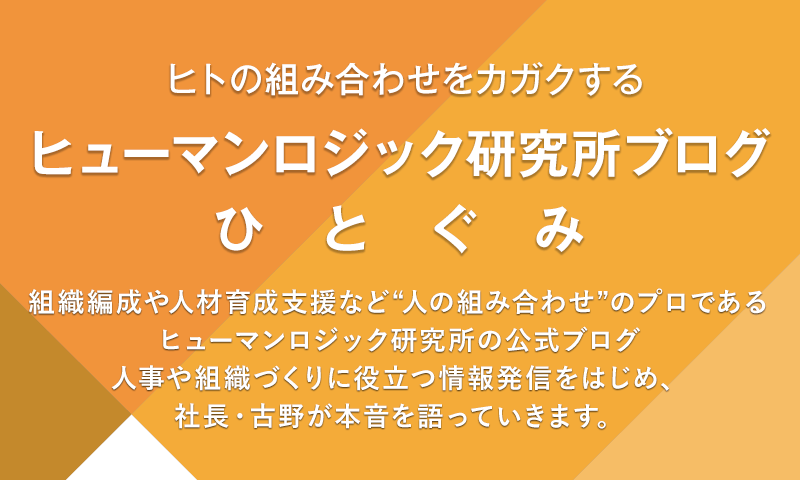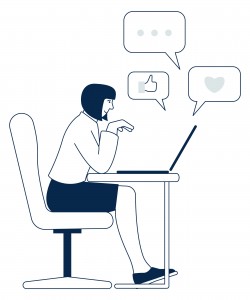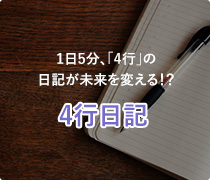古野のブログ
「日本人は議論下手。チーム議論がわかっていない」
2016.02.19
議論には「拡散と収束」が必要と言われています。
『拡散』とは、可能性を広げる議論です。『収束』とは、検証して着地させていく議論です。理想的な議論は、それぞれ可能性を広げて、多数の選択肢=可能性を出し尽くし、収束の段階で一つひとつ潰していき、一番最後に残るモノ(リスクが少なく可能性が高い)を選ぶことでしょう。これまで、企業研修や講座で「意思決定の議論エクササイズ」を千を超えるチームの議論を見てきましたが、議論がスタートして早い段階から収束するシーンばかりでした。
このエクササイズは、まず個人で考えて、それからチームとしての意思決定・合意形成を図るものです。彼らにコメントを求めると、異口同音に「早く合意することができて、良い議論でした」と答えます。個人で考えた案が同じであれば、理解もできますが、それぞれ違っていた場合でも合意に至るのは早いのです。その際どんなやりとりがあったかを掘り下げて質問すると「人の話を聞いているうちに、そうだなと納得して持論をさげました。対立はなかったです。皆が納得できたのだから、良い議論でした」なのです。
その背景は、「合意は早いに越したことはない」「全員が同じ案で合意出来たとなれば、それはいい案のはず」とニュアンスがあり、別の可能性を見出す気配さえなくなるのです。
一方、持論を固執する人が二人以上いたならば、対立軸を明確にして議論していきそうですがそうならず、お互いが持論を維持しつつ相手の案を尊重し「良いところ」を足していきます。二つの良い案を足し込んだ訳ですから、当然「良い結論」と評価していきます。もしくは「『二案を最終決定する』と合意した」として発表されることもあります。その理由を突っ込むと「可能性が広がるから」とまじめに回答してくれます。
二案を『足し込むこと』を宥和(smoothing)と言います。この宥和(smoothing)とは「大目に見る」→「二つの意見は似ているとし、共通部分に注目し、全体を丸くまとめる。争いにならない。弱みを見せない」ことです。(※P.ローレンスとJ.ローシュの研究から引用)
つまり、丸くまとめるため論点がボヤケ、本質的な議論になりません。二案だけでなく次々と足し込まれることもあり「テンコ盛り」状態になることもあるようです。また「二案を残す」という決定は、議論を避けたことになりますが、当事者たちは、本気で「良い合意だった」と思っている節があるのです。「対立を避けましたよね」と指摘すると、「ちゃんと議論して、共に分があるから二案なんだ」と食ってかかられたこともありました。
決めるということは、「一つに絞る」「他を捨てる」ことです。「二つ残すと決めた」うーん、確かに決めたのでしょうが…。

日本企業の会議では、上記のような合意形成が日々散見されているようです。「うちの会社の会議は、スムージングばかり」「結論を出さない会議が多い」と同様のコメントをたくさんいただいています。
これらの原因は、「対立なく合意する」ことは好ましいし、対立を避けることは相手を慮ることで〝オトナな対応〟と、二案を足し込んだり、二案共残したりするのです。社会学者のジャニスが指摘した「集団浅慮」はまさに〝慮った結果〟であり〝合意の幻想〟を表していると言えるのです。
また、ブルース・タックマンが提唱したチームの発展段階を示す「タックマンモデル」(形成・混乱・統一・機能・散会)においても、2段階目の「混乱(争い、不和)」を避けているようです。実は「混乱」を経ないと、昔風に言えば『腹を割った議論』をしていないため、次の「統一」以降に到達しないのです。
このエクササイズをこれまで数百回(のべ千チーム以上)していますが、過去最短で合意したチームがあります。それは東証一部上場企業で、部長以上を集めた幹部研修の時でした。合意に至ったのは、スタートしてなんと50秒です。5名とも同じ案だったので、一人が「その場に留まる」と言った途端、「俺も」「俺も」となり、『やっぱり留まるで正解だよね』と結論づけたのでした。別の案を疑う素振りはありません。残りの34分と10秒は延々と細かい順位づけに終始しました。
この企業は、業界シェアが60%以上という超優良企業です。この時、社長がオブザーブしていましたが、「日頃の会議と同じじゃないか。これでは新しいアイデアが出てくるはずはないね。制約のない議論でも全く広がらないのだから」と、危機感を示されたのが印象的でした。
ところで、なんで日本人は、議論下手なんでしょうね。(ちなみに外資企業で実施した際、チームに一人でも外人がいると必ず「論点」を明確にするプロセスが組み込まれていました)
それは、習慣性=文化の面と、個性の面から考える必要があるでしょう。
まず、基本的に文化的な背景から。
日本人は、主張し合って対立する議論に慣れていません。私はディベート経験者で、指導もしていますが、そこで感じるのは、「日本人の多くは意見と人格は同一視していて、反論することは相手を傷つける」と思っているようです。子供の頃から擦り込まれたというべきでしょう。ちなみに、米国は日常的に訴訟を起こす国ですが、訴訟は弁護士に任せて、本人たちは一緒にランチを食べている状態がよくあります。「意見と人格は違う」ので、『あの意見は間違っているが、君は友達』と平気なのです。そんな文化的な背景がありますから、対立することは厭わないし、慣れています。そのため、米国人のやりとりは、どこが論点になっているのかが明確になります。
しかし、日本人は対立を避けるため、論点がウヤムヤになりやすいです。例えば、あることで指摘すると「いや、そんなこと思っていなかった」「そんな風に聞こえたのであれば、言い直す」と回避することもあるのです。最近特に感じるのは、「質問に答えない」ことです。先に言い訳をしたり、はぐらかすような話しをしたり、他人事のように評論したり、聞いていなかったり。先の国会答弁をテレビで観る機会がありましたが、確か事前に準備しているはずなのに「答えない」答弁が多過ぎます。これが国を代表する人たちなのかと、悲しくなりました。
次に個性が影響して、原因となっているケースです。
日本人の平均値は、受容性が第一因子で、二番目が保全性です。「受け入れて、維持しようとする」のが特徴です。米国人の平均値は凝縮性、弁別性、拡散性という順番になります。「こだわりが強く明確に主張し、合理的に判断し、攻撃的である」が特徴です。日本人と真逆なのです。
日米のFFSの特徴から、日本では「受け入れる同士のやりとり」で、議論が「なあなあ」になりやすく、米国では「主張し合う同士のやりとり」で、議論は「対立軸が明確になる」のです。先ほど、文化的な背景からの話しをしましたが、それぞれの平均値という個性の特徴が文化形成にも影響を及ぼしているのです。一般的には、人々の特性がその国の民族性を構築していきますので、当然なんでしょうね。
さて、日本で良い議論をしていくにはどうすればいいのか?
日本人の受容性と保全性を活かすしかありません。保全性は、経験をいかに積み上げるかです。したがって、対立する議論を数多く体験し、『良い議論のモデル』を作り上げて、それを各自で少しずつ改善していくことでしょう。