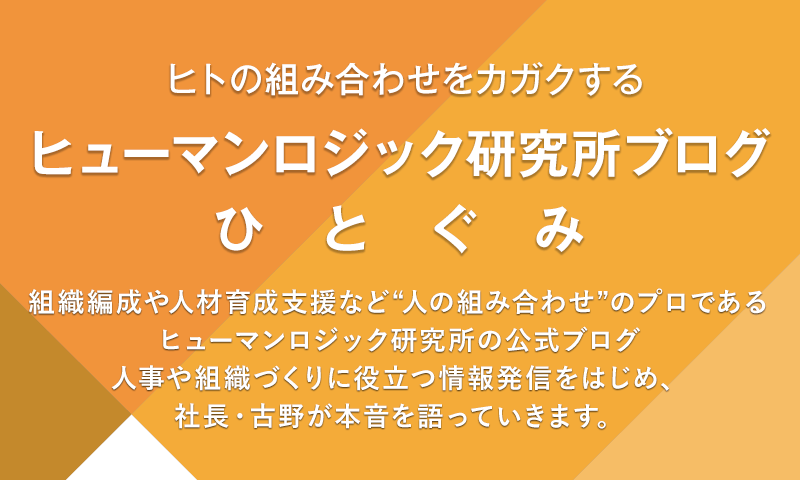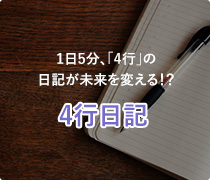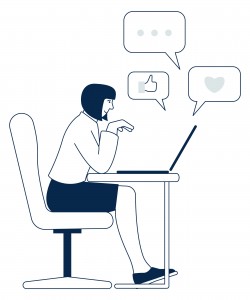今回取り上げるのは「F1地上の夢」です。
F1へ夢を追い続け、ワールド・チャンピオンとなったホンダ。その裏に隠された人間関係をナナメヨミ!
ナナメヨミ
第4回:理不尽な上司と楽しく働く方法を考える
2013.10.01
F1地上の夢

F1地上の夢 (朝日文芸文庫) 海老沢 泰久(著) 1993/06

参加する側のほうが楽しそうなスポーツ
モータースポーツというのはただ見ているよりも、自分がやる方が面白そうなスポーツだと思う。特にF1というカテゴリーは車の開発からレースまでのチームとしての競争自体が『レース』なので、レース場で単純に抜きつ抜かれつ楽しむようなスポーツではなくなっている。
80年代後半、ホンダの活躍でF1が地上波に流れるようになり、初めてF1というものを見るようになったときにはすでに抜きつ抜かれつのレースということは少なかった。当時の『ホンダエンジン』は他のメーカーに比較して圧倒的な力の差があり、自分も含めてその頃の子供達はその『技術的な力』にあこがれたものだ。
この本はそのホンダがF1に挑戦した第1期と第2期の最初ぐらいの期間、つまり、黄金時代を迎える前までの開発の過程を書いたノンフィクションである。読んでみるとやはりモータースポーツは見る側よりも参加している側のほうが面白そうだなと思ってしまう。困難な状況下で、自分たちの技術だけを頼りに世界に打って出て成功を勝ち取ろうとする様は、レースの結果以上の熱さに満ちている。訳のわからないまま難しい課題に直面してしまい侃々諤々やり合う人々の記録という感じである。
この本を初めて読んだのは高校生の頃だったかと思う。その時感じたのは『企業で何かを開発するのって面白そうだな(大変そうだけど)』ということだった。その後、理系の大学院を出て、ホンダの入社試験を受けてみたが受からず、別なメーカーに入り、なぜか研究開発には回されず、営業に配属されてしまった。そこから人生狂ってしまい、今人事コンサルの会社にいるのだが・・・というような個人の事情はさておき、改めて考えてみたいのは『ホンダで働くことはできなかったけれども、(あの頃の)ホンダのように働くことはできるのでは?』ということである。
世間では『倍返し』を叫ぶ中間管理職が人気だ。あんなにドロドロとした足の引っ張り合いをしたくはないが、まあ理不尽な上司というのは少なからずいるものなので、その理不尽な上司とどのように対すればいいのか、この本を参考に考えてみたい。
理不尽な上司と戦う方法
さて、ホンダのF1開発は、手探りの中、本田宗一郎という絶対的な権力者が『とにかくやれ』と号令をかけることで始まった。その情熱があることが、ホンダがF1活動を継続できた理由でもあり、苦労の源でもあった。『ただ勝つためだけにやっていれば、もっと効率的に開発する方法があったかも』、という思いと同時に『それじゃあ何も得られなかったのでは』という思いもあるようだ。
そして、この本田宗一郎という巨大な個性に個々別々の方法で対抗しようとする人々の歴史でもある。
ケース1 真っ向勝負してみる
初期のF1を監督していた中村良夫[i]は本田宗一郎と真っ向から対立した。『レースカーというのは極端な話、レースの時間だけうまく動けばいいのであって、常に機械として完全である必要はなない』と現場視点からものを言う中村と、F1を技術挑戦の場としてとらえ、『独自開発したF1カーで世界を席巻したい』と思っている本田とは完全に相容れない状態になってしまう。中村は第1期F1をホンダが撤退した後、本田宗一郎が社長を退任するまでヨーロッパから日本には戻ってこられなかったといわれている。
真っ向勝負は、互いに痛みが大きい。だが、この軋轢によって生じた課題を解決するためにホンダの技術陣はものすごいプレッシャーの中、仕事をこなさなくてはならなくなった。自動車メーカーとしてのホンダにとっては、後々の開発に活かされていくことになる。
ケース2 両方やってみる
ホンダのF1開発において技術的に大きな二つの山を越えることになる。一つは本田宗一郎が主張した空冷エンジンを若い技術者が否定すること、もう一つは第2期におけるエンジン主導の考えからターボを含めたバランス型への移行である。
空冷エンジンは本田宗一郎自身が最後の夢として技術開発をしていたものである。久米是志[ii]は空冷F1の開発責任者になり、試行錯誤を進めるが、技術的にはどうにもならないところまで行き詰まる。本田宗一郎のために空冷エンジンは成功させたい。だけど、成功の見込みはない。考え尽くしたあげく、久米は出社拒否をしてしまう。ここですぐに辞表ではないところ、また、1~2ヶ月ほったらかしにされて『戻ってこい』と怒鳴るだけで元の仕事に戻してしまう上司側の配慮もすばらしい。
しかし、この手段を行う場合、上司側の要求を考え尽くした結果、『どうしてもダメです』といえるということが重要になる。つまり、上司の言うことは筋が悪いと思っても、その方向で徹底的にやってみるという過程が必要になる。同時平行で自分のやり方で仕事を進めておいて、できれば実績つきで事後承諾させるというのは手っ取り早い方法かもしれないが、その場合は自分の考えた方法は必ず成功させないといけないし、責任も重くなる。それでも、やってみて成果が出れば上司もそれを否定するほどの理不尽はしないだろう。この本の中では比較的よく使われている手法であり、川本信彦[iii]は自分がマネジメントの立場になったとき部下が自分の考えとは違うことを隠れてやっているのがわかって、『あの頃、上司に隠れて自分がやっていたことは、全部知られていたんだなぁ』と述懐している。
ケース3 さりげなくやってみる
初期の車体を担当した佐野彰一[iv]は、車体に効率的に載せることを考えていない大きなエンジンをどのように効率的にレイアウトするべきかを試行錯誤することになる。これは、車はエンジンが主でシャーシはそのエンジンを載せるためのものといった当時のエンジン優位の会社の考え方があったためだったらしい。
その結果出てきたデザインはエンジンに負荷がかかりそうなレイアウトだったため、エンジン技術者から反対されてしまう。しかし佐野は『丈夫そうなエンジンだからどんな設計にも絶えられますよ』機械としてがっちり作られたエンジンだったことを逆手にとって切り返し、自分の設計を通すことができる。
自分が譲れない重要なところ以外は相手に譲って、なだめながらさりげなく通す、といった形で自分なりに課題を消化していくのも一つの手である。これを実現するためには譲歩できるポイントを見極められる高い専門性と冷静さが必要になりそうである。
理不尽を通り抜けてしまうと、理不尽さは笑い話になってしまう
理不尽な状況に置かれても、それを克服しようとする人もいれば、それを甘んじて受け入れてしまう人もいる。もちろん、取り組むテーマが面白いという前提はあるだろう、だが、他人の考えの筋が悪いので相対的に自分の考えの筋がいいということにはならない。結局自分自身でいい筋の考えを見つけなければいけないし、それを譲らずに理不尽な環境でどう実現するかということが問われているように思われる。
結局、(あの頃の)ホンダのように働くために大事なことは、自分で自分の仕事を完成させるという意志を持つと言うことだろう。意志を持ったらそれを実現するために自分で動かなければいけないし、それを実現する自分なりの方法というのを見つけなければならない。
上司が反対する、周りの環境が整わないからできないのではなく、上司が反対する、周りの環境が整わない中で自分が何をするか?と考えた場合、結局頼れるのは自分だけである。
[i]中村良夫 第1期 ホンダF1チームの監督を勤めた人物
[ii]久米是志 第3代 本田技研工業 代表取締役社長
[iii]川本信彦 第4代 本田技研工業 代表取締役社長(第1期から第2期F1開発の中心にいた人物)
[iv]佐野彰一 第1期のF1におけるシャーシ開発を行った技術者
~ホンダのF1参戦の略歴~
第1期、1964年~1968年 (5年間で2勝)
シャーシ、エンジン含め全て自社製造しフルワークス体制でチームとして参戦。
当初、エンジン供給のみの参戦予定であったが、シーズン開幕直前にキャンセル
されてしまい、フルワークスとしてとして参戦。
当時のホンダは、2輪メーカーとしてのレース実績はすでにあったが、4輪メー
カーとしてはほぼ実績がない状態での参戦となった。
第2期、1983年~1992年 (10年間で69勝)
既存チームにエンジンを供給するという「エンジンサプライヤー」としての参戦。
1988年にマクラーレンホンダが16戦中15勝したことを筆頭に5度のコンストラク
ターズタイトル(年間タイトル)を獲得。87年には鈴鹿サーキットでF1が開催
されるようになり、日本国内でもF1が認知されるようになった。
第3期、2000年~2005年
当初エンジンのみを供給し、後にフルワークス体制のホンダF1チームに移行。
第4期 2015年以降 参戦予定