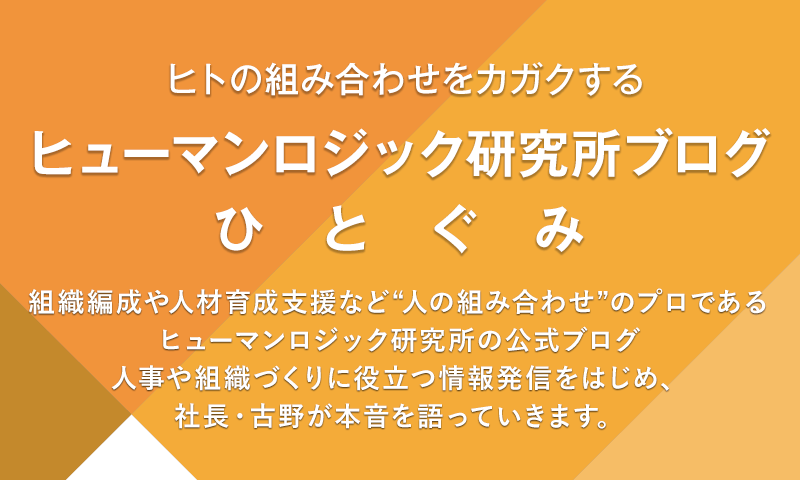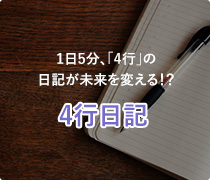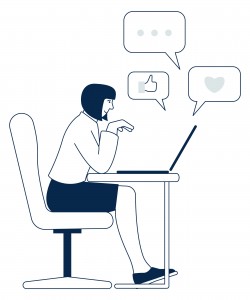最初に取り上げるのは、『ローマ人の物語』に書かれているカエサルとアウグストゥスである。全ての優秀なリーダーがおそらく一番苦手としていることである『後継者指名』ということを考えるための事例としてみたい。
ナナメヨミ
第1回:優秀なリーダーはどこまで見えているのか?
2013.06.11
第1回は『ローマ人の物語』
文庫版『ローマ人の物語13 ユリウス・カエサル ルビコン以後(下)』塩野七生 2004/10(1996/3)

『世界史上屈指の、後継者人事の傑作 』
さて、どんな組織においても組織が大きくなっていく過程においては『拡大期』と『安定期』どちらも正しく運用される必要がある。企業や組織の発展段階でそのようなことが起こることは様々な経営学の論説でも指摘がある。
同時に、『拡大期』を指揮するリーダーは既存の価値観を壊し、新たな価値観を提示し、それが既得権益層から疎まれてもはねのける強さ(鈍感さ)が必要になる。『安定期』を指揮するリーダーは『拡大期』で棚上げした問題の解決をしなければならない。成長拡大していることで納得していた問題を、ルール化、システム化していく必要がある。
つまり、『拡大期』と『安定期』で求められるリーダー像は異なるということになる。
そのため、拡大に強いリーダーは安定には弱く、安定に強いリーダーは拡大には弱い。特に、自分の方法論で成功した人であればあるほど「自分のやり方は正しい」と考え、失敗する物である。同時に、人間は同じ傾向の人間を高く評価しやすい。だから後継者指名もどちらかといえば「自分の路線を引き継いでくれる人」を希求しやすいものであるといえる。
このあたりに優秀なリーダーが優秀であればこそ後継者問題を間違える理由があるように思われる。後継者には「自分を超える後継者」が必要なのではなく「自分と違うことができる後継者」が必要になるのである。
さて、『ローマ人の物語』で書かれているカエサルがどういう人かというと、簡単に言えば国家発展のため新たな価値観を創造した天才であるが、同時に非常に人間味があり、面白みのある人物として書かれている(塩野先生が大好きなのもあるが・・・)。ヨーロッパの原型になる地域を征服した軍人であり、共和制の限界を見切って帝政への道筋を開いた政治家でもある。
実はこの、ローマにおける『皇帝』という役割が微妙で、純粋な絶対者としての『王様』というよりは、『終身の大統領』というほうが近いようだ。ローマは皇帝が統治するようになっても議会は残り続け、民衆の支持を失った皇帝は排除される(暗殺されてしまう)という流れはその後も一貫している。しかも、ローマでは王政の時に国が傾いたという歴史があるため王政アレルギーがあるのだ。そのため終身独裁官となったカエサルは反動的な共和派に暗殺されてしまったわけである。
人間的にも、愛人をたくさん抱え、クレオパトラと浮き名を流し、若い頃から借金王で、極めて人間的なエピソードの多い、民衆の人気者である。そういった人間味と創造性を持った理想的な『拡大期』のリーダーであるカエサルの後継者がオクタヴィアヌス(後のアウグストゥス)だった。
カエサルは軍事上の副将を勤めていたアントニウスを無視して親戚の子供だったオクタヴィアヌス(アウグストゥス)を自分の後継者に指名した。もちろん自分が暗殺されることは考えていなかったこともあるだろうが、後を継いだときのウグストゥスはまだ18才の無名の若者である。しかも、アウグストゥスに統治の才能はあるが軍事の才能は無いことまで見抜いて腹心(アグリッパ)。18の若者に腹心となるべき人材まで付けたのだから、本気で育成するつもりだったのだろう。
この後、アウグストゥスはこの役割を見事果たすことになる。アントニウスとの後継者争いに勝ち、帝政(皇帝が決断をし、官僚機構が補佐するようなシステム)を構築していくことになる。その後のいわゆる『帝政ローマ』の基礎的な政治システムはほぼアウグストゥスが作ったものである。税制、軍政、公共事業、内閣、地方分権などはアウグストゥスが整理し、説得し、浸透させたものである。
このあたりに優秀なリーダーが優秀であればこそ後継者問題を間違える理由があるように思われる。後継者には「自分を超える後継者」が必要なのではなく「自分と違うことができる後継者」が必要になるのである。
隙あらば暗殺も辞さないという人々に向かって、(本人達の)リストラやら、権限の縮小といった後々自分達の首を絞めるかもしれないことを提案し承認させなければいけないのだから、それを乗り切ってしまう政治力からすると後継人事の傑作といわれても申し分ないだろう。
『多くの人は、見たいと欲する現実しか見ていない』
さて、カエサルがなぜそんな優秀な後継者を選べたのか?カエサルがどのような考えでアウグストゥスを選んだのか?確実な資料は残っていない。だが、カエサルの人となりからこんな推察ができるのではないかと思っている。
カエサルをどのような人材と見るか、私の個人的な見方でいうと、どちらかといえば理想に邁進するタイプではなかったと思う。単に、『現実に会わないものを大胆に変えていったら結果、リーダーになった。』という感じではないだろうか。『ローマを発展させるためにどうしても独裁者になりたかった』というよりは、『今の国をうまく動かすには、自分一人で決めた方が多人数で議論するより楽だ(どうせ議会は意志決定を投げてくるし・・・)』という感じではなかっただろうか。
本の中で繰り返し出てくる、カエサルが言ったとされる『人は見たいと欲する現実しか見ない』という記述からして、カエサルが、ある種人間の限界についてよくわかっていた人なのだろうと思われる。『所詮、人のできることは・・・』という現実的判断から離れていないように思う。
アントニウスは軍人としては優秀であるが、最終的にクレオパトラに籠絡されてしまったりする、ある意味、人間的な人であったようだ。現場のリーダーとしてはきっぷも良さそうだし、信頼もあったようである。カエサルが気に入りそうないわゆるかわいい部下だったのではないだろうか。だが、そんなことには流されず、カエサルはアウグストゥスを指名した。まさに、情としてはアントニウスだが、現実的な利としてアウグストゥスだったのだろう。
一番重要なのは、カエサルがある意味、理想を極めた人でありながら、最終的に現実を捨てなかったということである。このあたりに真に優秀な人の思考という物が現れているように思う。
時代を見通す「本質的な客観性」
さて、カエサルができて、他の人ができない後継者人事で、カエサルが持っていた物とは何だったのだろうか?
言葉が正しいかどうかは疑問だが、個人的には「より本質的な客観性」というようなものだったのではないだろうかと思っている。現実に対して可能なことはすべて行うが、過度な期待も抱かない。理想的で完全な善であるような神や人間を仮定しないと共に、欲望に迷い、すぐに堕落してしまう人間や神を悪だとも思わないというような、人間や社会に対してある種の達観、それ故、人間社会をより良き方向に導ける可能性があるというように考えられるといった感じである。
というようなことを頭で理解しても、なかなか実現するのは難しい。結局そういった人間的、社会的な本質を悟るための人間的な成熟を目指して人は生きていく物なのかなと考えたりもする。